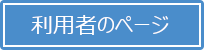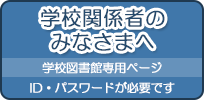高槻ゆかりの歌人 -伊勢と能因-
伊勢
 伊勢
伊勢
宇多天皇の后であった、温子に仕えた女房です。
父、藤原継蔭が伊勢守であったため、伊勢とよばれました。
早くから歌の才能を発揮し、勅撰和歌集「古今和歌集」には小野小町の18首をしのぐ22首が選ばれています。優美な歌風で古今集時代屈指の歌人です。
 伊勢廟堂
伊勢廟堂
家集に「伊勢集」があり、後の紫式部の源氏物語はこの家集に依るところが多いのではないかと言われています。(平安文学論集)
 伊勢寺山門
伊勢寺山門
伊勢寺には伊勢のものと伝えられる、硯、銅鏡が収められています。
古曽部で詠んだと言われている歌
見る人もなき山里のさくら花
ほかのちりなんのちぞさかまし
(伊勢集)
能因
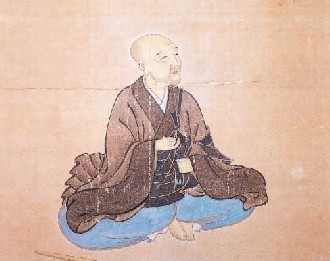 能因法師
能因法師
俗名を橘 永愷といいます。
永延2年(988)、 橘 元愷の子として生まれました。
藤原長能に師事し、歌を学びました。
歌の師匠を持った初めての歌人で、師伝相承のはじまりと言われています。
中古三十六歌仙の一人。
 能因顕彰碑
能因顕彰碑
しかし、僧侶でもなく、俗人でもなく、諸国を旅して歌の道を究めました。後の西行、芭蕉もこれに倣ったと言われ、僧侶歌人としての初めての人です。
枕詞にあるその地方を訪ね、歌学書「能因歌枕」を著わし後の歌人に大きな影響を与えました。
勅撰和歌集、「後拾遺和歌集」には、31首の歌が選ばれています。
 能因法師墳
能因法師墳
「能因塚」「文塚」などの史跡が今に伝えられ古曽部で詠んだ歌もあります。
津の国古曽部といふ所にてよめる
わが宿のこずゑの夏になるときは
生駒の山ぞみえすなりゆく
(後拾遺和歌集)